タマモクロス本紀~白の伝説~
『静かな運命』
種牡馬となったタマモクロスは、非常に安定した産駒成績で、長年内国産種牡馬としてのトップクラスの地位を保ち続けた。彼の代表産駒としては、AJC杯(Gll)など重賞を3勝したカネツクロス、シンザン記念(Glll)、チューリップ賞(Glll)を制したダンツシリウス、京都記念勝ち馬(Gll)勝ち馬マイソールサウンド・・・などと、Gl馬こそ出していないものの、多くの重賞馬を輩出した。全盛期には、種牡馬ランキングベスト10の常連にもなっていた。彼の産駒は、父と同じように晩成の傾向が強く、5歳(現表記4歳)ころに本格化して安定した戦績を残すという特徴も持っていた。
ただ、タマモクロス産駒のデビューを誰よりも心待ちにしていた馬主の三野氏は、タマモクロス産駒のデビューを見ることなく、この世を去ったという。現役引退を惜しむ声を押し切って5歳いっぱいでの引退にこだわった彼の思いは、結局果たされなかったのである。これもまた、運命というものだろうか。
こうして種牡馬としても多くの重賞馬をターフに送り出し、馬産地では一定の存在感を保ち続けたタマモクロスだったが、一般のファンの間では、次々と現れる名馬、名種牡馬たちによって、次第に影が薄くなっていくことは避けられなかった。時の経過とともに、種牡馬としての評価は定まっていったものの、逆に彼の名前が一般のファンの口に上ることも少なくなっていった。
『天に還る時』
だが、2003年4月10日、突然タマモクロスの名前がテレビや新聞・・・それも、一般ニュースや全国紙にとりあげられた。それは、彼自身の訃報によってだった。
タマモクロスは、死の前日朝まで健康に問題なく、26頭の繁殖牝馬への種付けも済ませていた。ところが、同日昼に突然苦しみ始め、生命も危ぶまれる事態に陥った。腸ねん転を発症したのである。
草食動物であるサラブレッドの腸は、肉食動物、雑食動物に比べて非常に長く、それだけにその腸がねじれを起こす腸ねん転は深刻な影響をもたらし、死につながることも少なくない。タマモクロスも、10日には一時回復の兆しをみせたものの、夕方には再び容態が悪化し、そのまま息を引き取ったという。こうして現役時代に鋭い末脚でファンを沸かせ、「元祖・芦毛の名馬」ともいうべき存在としてファンに親しまれたタマモクロスは、不帰の客となった。
この時の報道では、一般ニュースや全国紙が「競馬ブームの火付け役となった天皇賞馬の死」としてその死を広く伝えたのに対し、競馬マスコミは比較的冷静だったことが印象的である。社会現象としての競馬ブームが一般マスコミにも広く認知された半面で、競馬界自身にとっては、それはもはや過ぎ去った過去のものとしてしか扱われなかったとすれば、それもまた皮肉な話である。
『生き続けるもの』
しかし、時代の転換期に競馬界に忽然と現れ、そして去っていったタマモクロスが競馬界に残したものは、今なお競馬界に息づいている。
タマモクロスがターフを去った後、中央競馬はオグリキャップを中心とする「平成三強」の時代へと突入していった。だが、タマモクロスの存在と、彼が築いた時代は、一般的にはオグリキャップら「平成三強」によって築かれたとされる中央時代の黄金期の基盤として競馬界に多大な貢献を残した。
「平成三強時代」を支えた新しいファンのうち、「タマモクロス対オグリキャップ」という昭和最後の決戦に魅かれて競馬に入ってきた割合は小さくない。彼らの対決は、「芦毛」という素人にもひとめで分かる毛色の名馬同士の戦いであるがゆえに、新規ファンの開拓により貢献した。JRAや競馬マスコミ自身が彼らの対決を「芦毛対決」として煽りたて、それぞれの背負った物語を広く伝えることによって、ファン層を大きく拡大していった。
また、当時の競馬界には、「芦毛の馬は走らない」という迷信が確かに存在していた。それ以前の芦毛の強豪といえば、メジロアサマ、メジロティターンという父子二代の天皇賞馬、そして唯一のクラシックホースである菊花賞馬プレストウコウが挙げられる程度である。彼らはいずれも今でいうGlレースの勝ち馬ではあるにしても、長期にわたり安定した戦績を残すことはできなかった。彼らは、「名馬」と呼ぶには一歩も二歩も足りない存在にすぎなかったのである。そのため、調教師たちにも「芦毛は嫌い」「芦毛は預かりたくない」という偏見が少なくなかった。
しかし、タマモクロスとオグリキャップは、それまでの芦毛の馬たちとはまったく違っていた。彼らはいずれも「古馬最強馬」と「4歳最強馬」の名に恥じない実力と実績を残してきたし、それぞれの道で連勝街道を突っ走ってきた彼らによる直接対決は、競馬史になかった魅力を持っていた。新時代の到来を前にして彼らが競馬関係者たちに「芦毛に名馬なし」という迷信が誤りであることを実証したことにより、「タマモクロス、オグリキャップ以降」も、メジロマックイーン、ビワハヤヒデといった芦毛の名馬が次々と出現して競馬人気を支えており、この時代は「芦毛の時代」とも呼ばれている。
タマモクロス・・・それは、時代が「昭和」から「平成」に変わる直前に現れた名馬であり、新世代の旗手となるべきオグリキャップの前に大きな壁として立ちはだかることで、競馬界に新しい時代の到来を告げる役割を果たした。「白い稲妻2世」「風か、光か」と謳われた彼こそは、時代に求められ、時代を築いた名馬だったということができる。
そんなタマモクロスも、もうこの世にはいない。その訃報に
「昭和は遠くなりにけり―」
と感じたファンは、決して少なくないことだろう。
しかし、タマモクロスは死しても、彼が残したものは「今」へと生き続ける。競馬が続く限り、積み重ねられた歴史が消えることはなく、タマモクロスの輝きが失われることもない。そして、タマモクロスたちが切り拓いた時代に続いた名馬たちの戦いは、さらなる未来をつむいでゆくのである―。
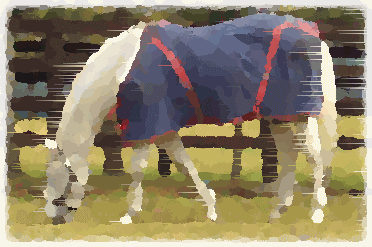
時代が「昭和」から「平成」に変わる直前に現れ、新世代の旗手に大きな壁として立ちはだかって「風か光か」と謳われた彼こそが、時代に求められ、時代を築いた名馬だった…