ウィナーズサークル列伝~芦毛の時代、未だ来たらず~
『新たなる戦いの序曲』
ダービーを制したウィナーズサークルは、ダービー後は「世代ナンバー1」といわれ、秋にかけて菊花賞(Gl)の本命馬として挙げられることになった。ダービーを見事なレースぶりで制した馬が菊花賞戦線で人気になるのは、ある意味で当然のことである。しかも、ウィナーズサークルの父は長距離を得意とし、2頭の天皇賞馬を輩出したシーホークであることから、期待を集める要素も揃っていた。
しかし、ウィナーズサークルの独走を許すほどにライバルたちも甘くはなかった。まず春には大敗続きで評価を大きく下げていたサクラホクトオーが、セントライト記念(Gll)では鮮やかな復活劇を遂げた。神戸新聞杯(Gll)では、春は裏街道で力を蓄えていたオサイチジョージが、他を寄せつけずに完勝した。秋のクラシック戦線は、春とはまったく異なる結果が続き、勢力図が大きく塗り変わりつつあった。
ウィナーズサークルの復帰戦は、当初、セントライト記念が予定されていた。しかし、松山師は最終的にはこのレースを見送って、京都新聞杯(Gll)から始動させることに決めた。このレース選定の背景には、菊花賞の舞台となる京都の芝コースを、本番前に一度経験させておきたいという考えがあった。それまでデビュー戦の福島以外では中山と東京でしか走ったことのなかったウィナーズサークルにとって、これが初めての西下だった。
ウィナーズサークルが駒を進めた京都新聞杯には、当時としては例年どおり、菊花賞を目指す強豪たちが顔を揃えていた。ダービーでの半馬身差の逆転を目指すリアルバースデー、1番人気で5着に沈んだダービーの雪辱を誓うロングシンホニー、弥生賞大差勝ちの後脚部不安を発症して休養していたレインボーアンバーといった春の既成勢力に対し、重賞2連勝中のオサイチジョージ、夏に急成長した上がり馬バンブービギンといった新興勢力が挑むという構成である。
ウィナーズサークルは休養明けということもあって、神戸新聞杯を勝ってきたオサイチジョージに次ぐ2番人気にとどまった。ウィナーズサークルは調整の遅れも報じられており、京都新聞杯はあくまで叩き台といわれていた。
そして、ウィナーズサークルは好位につけて第4コーナーで先頭に立ったものの、やはり完調ではなかったのか、直線で粘り切れず、4着に敗れた。
だが、この敗北は必ずしもウィナーズサークルの評価を下げたわけではなかった。当時は「京都新聞杯の勝ち馬は菊花賞を勝てない」というジンクスもささやかれていて、直近のトライアルで全力を燃やし尽くした勝ち馬より、そこそこ走った有力馬の方が、本番では一番強い・・・という声もあった。そして、ウィナーズサークルの京都新聞杯での戦いぶりは、まさに後者に当たるものだった。
『宿命』
実際、本番が迫る中での報道では、ウィナーズサークルは京都新聞杯のひと叩きで気配が一変しており、追い切りでの素晴らしい走りは、馬がようやく走る気になったかのようだ・・・とされていた。そうした気配を受けた菊花賞(Gl)では、京都新聞杯を勝ったバンブービギンに1番人気を譲ったものの、僅差の2番人気に支持された。
しかし、菊花賞でのウィナーズサークルは、期待に反してまったくいいところがなかった。レース当日に発表された馬体重は、京都新聞杯より16kgも増えていた。レースでの彼も、スタートから中団に付けたのはいいが、馬体重の増加分を引きずったかのように、勝負どころの直線での反応は鈍かった。彼はダービーでみせた差し脚を再現するどころか、むしろ後ろに差されていく体たらくに終わったのである。ウィナーズサークルが持つはずの豪脚も、父シーホーク譲りのスタミナも全くの不発に終わり、まさかの10着に敗れた。
すると、レース後まもなく、その謎は解き明かされることになった。ウィナーズサークルは、この日のレース中に骨折していたのである。その後しばらくは復帰への努力が続いたものの、脚の回復状況は思わしくなく、結局そのまま引退が決まった。そんなウィナーズサークルについて、後年、松山師は
「本当にダービーを勝つために生まれてきて、ダービーで終わった。宿命だね」
と語っている。
なお、この年のクラシック馬たちを見ると、菊花賞を制したバンブービギンも、その菊花賞を最後に故障で引退に追い込まれている。最後に残されたのは、皮肉なことに菊花賞は回避した皐月賞馬ドクタースパートだけだったが、その彼も長い不振へと落ち込んでいく。ダービー馬と菊花賞馬を失った「平成元年クラシック世代」は、古馬戦線では、「強い」と言われた昭和63年世代と平成2年世代に挟まれ、苦しい戦いを強いられてゆくことになる。
『もうひとつの使命』
同期生たちが異世代との戦いに苦しむ一方で、もはやより速く走るという競走馬としての使命を果たすことができなくなったウィナーズサークルは、サラブレッドのもうひとつの使命・・・後世に優れた血を残す種牡馬としての使命を果たすために、北海道の三石で種牡馬入りすることになった。
種牡馬入り当初のウィナーズサークルは、「日本ダービー馬」の金看板もあって、当初は配合相手にそこそこ恵まれた。毎年50頭程度の牝馬と交配された彼は、産駒の数も40頭前後を確保した。
もっとも、種牡馬としてのウィナーズサークルの仕事ぶりは決してまじめではなく、むしろ怠け者ぶりを発揮していたとのことである。・・・レースでも他の馬を抜くのが嫌いだった平和主義者のウィナーズサークルにとって、競走馬を引退してやっと戦いから解放されたというのに、さらに種牡馬としての仕事として戦いを強いられることは、迷惑だったのかもしれない。
しかし、ウィナーズサークル産駒が競馬場でデビューする頃、中央競馬には血統革新が起こりつつあった。馬産界でも、スピード化の流れに対応できる輸入種牡馬が優遇される反面、内国産のステイヤー血統は、以前よりも需要が大きく落ち込んでいった。
『ロスト・ユートピア』
ウィナーズサークルと同じ年に生まれ、そして同じ年に初年度をデビューさせたのが、あの米国二冠馬サンデーサイレンスである。ウィナーズサークルが日本ダービーを制した1989年5月28日の1週間前にピムリコ競馬場のプリークネスSでケンタッキーダービーに次ぐ米国二冠を達成し、ウィナーズサークルの最後のレースとなった菊花賞の前日にガルフストリームパーク競馬場のBCクラシックで米国競馬の頂点を極めた歴史的名馬は、引退後ただちに日本へ種牡馬として輸入されると、暴風のような威力をもって、瞬く間に日本の馬産界を席巻した。 くしくも馬産地で種牡馬として激突する形となった日米のダービー馬だが、その結果は、あまりにも無惨な現実として現れた。
彼らの初年度産駒が3歳馬として競馬場にデビューした94年、米国のダービー馬であるサンデーサイレンス産駒はJRAで32頭がデビューし、そのうち20頭が重賞4勝を含む30勝を挙げて約4億9000万円を稼ぎ出す一方、日本のダービー馬であるウィナーズサークルは、JRAでは13頭がデビューしたものの、そのうち3頭が5勝を挙げ、約8500万円を稼いだに過ぎない。
そして、翌95年には、サンデーサイレンス産駒は62頭が重賞11勝を含む100勝を挙げ、約25億円を獲得してリーディングサイヤーを奪取した一方、ウィナーズサークル産駒は、9頭のうち2頭が3勝を挙げ、約4400万円を稼いだだけで終わった。ウィナーズサークル産駒の賞金獲得額は、初年度産駒がデビューした94年がピークであり、その後、その数字を上回ることはなかったのである。
ウィナーズサークル産駒の多くは、JRAではなく地方でデビューし、中には息長く活躍して何勝も挙げる馬が出た。高崎ダービーを制したウィナーズキシュウのような強豪も現れている。しかし、彼らの活躍は、馬産地やファンの視線をウィナーズサークルに向けさせるきっかけにはならなかった。ウィナーズサークルのJRAでの種牡馬成績は、複数の2勝馬がいるものの、重賞戦線で活躍するような産駒は現れなかった。
そして、時の経過によって、日本ダービーの栄光の記憶が遠ざかるとともに、ウィナーズサークルの種付け数も減少傾向をたどり、供用6年目にあたる1997年には、ついに一桁に落ち込んだ。競走馬としては故障の悲運に遭ってその使命を果たし得なくなったウィナーズサークルだったが、その先に待っていたのは、やはり平和な楽園ではなく、過酷な戦場だったのである。
2001年ころ以降は故郷の茨城県にある東大農学部附属農場へと移動したウィナーズサークルだが、その後に送り出した茨城県産のサラブレッドたちも頭数は極めて限られ、結局自らの名を父として再び蘇らせることはないまま、2016年8月27日には天寿を全うしたという。
『戦いに生きたきみのために』
種牡馬としては成功することができなかったウィナーズサークルだが、彼の名は、ただ1頭の茨城産、そして芦毛のダービー馬として、今なお日本のサラブレッド史に刻まれている。
彼が持ついくつかの「ただ1頭の」という冠の中でも、「芦毛の日本ダービー馬」という部分は、おそらく歴史とともに、いつの日か失われる日が来るだろう。だが、彼が芦毛馬たちのために切り拓いた道、そして人々に与えた希望は、その冠が失われたとしても、永遠にその輝きを失うことはない。むしろ、後に続く者たちが続々と現れてこそ、彼の業績も輝きを放つ。
「芦毛の時代」と呼ばれた1988年(昭和63年)から1994年(平成6年)頃にかけて、ウィナーズサークルの業績が高く評価されることはなかった。しかし、彼が他のどの芦毛の名馬も果たし得なかった快挙を果たしたことは、間違いない事実である。事実と実績によって覆された「芦毛馬は走らない」という迷信の終焉に対して彼が果たした役割は、日本競馬における日本ダービーの位置づけの大きさからは、決して過小評価されるべきではないだろう。
競馬界が迷信から解放された現在、再び「芦毛の時代」が来るとしたら、それは今度こそ他の馬たちと等しく扱われるようになった芦毛馬たちの中から、日本競馬の最高峰としての日本ダービーを制する名馬たちが次々と現れるようになるかもしれない。その暁にこそ、ウィナーズサークルが果たした歴史的な役割は、人々に広く語られ、認められるようになるのだろうか。
そのわかりやすい毛色ゆえに、「芦毛ファン」までいるのが芦毛馬である。しかし、日本の芦毛の歴史は、差別との戦いの歴史でもあった。我々は、本当の意味でスターホースとは呼ばれなかった馬たちの中にも様々なドラマがあったことを知っておきたいものである。
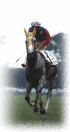
日本競馬界史上ただ1頭の芦毛のダービー馬は、勝者のみが立つことを許される場所と同じ名前…