サクラスターオー列伝~消えた流れ星~
『散りゆく花』
サクラスターオーの病状は、少しずつ、しかし確実に下降線をたどっていった。日に日に弱っていくサクラスターオーを見た平井師は、患部にボルトを埋め込む手術をすることを決断した。9本のボルトを入れることで、少しでもその脚にかかる負担を支えるためである。危険な手術ではあったが、今決断しなければ、助かる見込みはゼロになってしまう。
4月に入り、桜が花開く季節となった。前年に「サクラ」の勝負服を背負って皐月賞という大舞台に輝いたサクラスターオーは、その1年後に、死を賭した手術に臨もうとしていた。
サクラスターオーの手術は、極秘のうちに行われた。春のクラシックシーズンを控えているのに迷惑と心配をかけるとして、東騎手にさえ予定は教えなかった。
5時間にわたった手術は、「いちおう」成功した。手術をしたという知らせ、そして手術が成功したという知らせを同時に聞き、とるものもとりあえず夫人とともに見舞いに駆けつけた東騎手だったが、彼はサクラスターオーの姿を目にして呆然とした。酸素吸入ボンベをくわえたサクラスターオーの左前脚は、手術の後遺症で何倍にも腫れ上がっていた。
「頑張れ、頑張れよ、頼むよ、頑張ってくれよ、スターオー」
東夫人は、東騎手がサクラスターオーに必死でそう語りかけていたのを聞いている。くしくも、この日は朝から冷たい雨が降り、この雨はやがて季節はずれの雪に変わり、桜の花びらを散らしていったという。
『起こらなかった奇跡』
このように懸命の治療と介護が続けられたサクラスターオーだったが、手術の後も、状況が好転することはなかった。
体力をつけるために、大幅に減らしていた飼い葉を与えると、最初のうちはすべて食べていたサクラスターオーだったが、やがて食べる量が減り、口にしなくなってしまった。当時のサクラスターオーの様子について、東騎手は次のように評している。
「だんだんこうしてもよくならないと分かったのか、あるいは生きていくことへの執念がなくなったのか・・・」
さらに、人間が手を触れる・・・というより、近づくことさえ嫌がって暴れるようになった。その暴れ方も激しく、せっかく手術をしてはめこんだボルトのうち2本が外れてしまい、再手術をしなければならなくなった。
「どうしてこんなに俺を苦しませるんだ、と怒っていたんだと思う。僕らは彼のために良かれと思ってやったことだけど、スターオーにとってはいたずらに苦痛を伸ばしているように思えた。彼の目には、僕らは鬼のように映っていたんでしょう。でも、それは当然のことかもしれない・・・」
・・・ただ、そんなサクラスターオーも、近づいて手を触れるのが慣れ親しんだ厩務員である時だけは、決して暴れなかったという。
4月下旬に入り、桜の花びらが散りきったころ、サクラスターオーは自力で立ち上がることもできなくなった。体温は39度を越し、腰は床ずれを起こしていた。既に、彼の身体はぼろぼろになっていた。
「あいつは苦しんで苦しみ抜いて、疲れ果てちまったんだ。それが痛いほどわかるんだ、俺には・・・」
後になって、平井師はそう話している。
『流れ星、消えた』
1988年5月12日、境勝太郎調教師と稲葉幸雄調教師が、サクラスターオーの見舞いに訪れた。境師と平井師の縁は前記したとおりであり、稲葉師も平井師のもともとの師匠にあたる。
いずれも競馬界に知られた名調教師である2人は、闘病生活を送るサクラスターオーの姿を見て絶句した。・・・かつて450~460kgほどあったはずのサクラスターオーの馬体は、脚への負担を軽くするために体重を極限まで落とした上、故障、そして手術による衰弱もあって、250kg前後になっていた。やせ衰えたサクラスターオーの馬体に、極限まで鍛え抜かれたサラブレッドの美はもはやなかった。彼らの口から、思わずこんな言葉が漏れた。
「雄二、もうそろそろ眠らせてあげたらどうだ。楽にしてやれ・・・」
「これだけ頑張ったんだから、しようがない・・・オーナーには、俺たちが話してやるから・・・」
その言葉を聞いた時、平井師はそれまで自分を踏みとどまらせていた何かがぷっつりと途切れたような気がするという。それまでこらえていた涙があふれた。
その後、サクラスターオーの関係者たちが平井厩舎へ集められた。平井師は、境師、稲葉師の申出を辞退し、全氏に対しても自ら連絡した。しかし、平井師からサクラスターオーを安楽死させたい旨を伝えられて、反対する者はいなかったという。平井師、そして平井厩舎のスタッフの懸命の治療と介護、そしてサクラスターオーの苦しみを知っていれば、その平井師がついに下した決断に反対することなど、できるはずもなかった。
関係者が最後の「お別れ」に行った時も、サクラスターオーは懸命に立ち上がろうとした。
「もう立たなくていいんだよ、立たないで、お願いだから立たないで・・・」
という声は、彼らのすべての共通した思いだったのだろう。
その日のうちに、サクラスターオーに安楽死の処置がとられた。発熱で火のように燃えていたサクラスターオーの身体は、1本の注射によってその灯火を消し、やがて水のように冷たくなっていった。
サクラスターオー、悪夢の有馬記念から137日間の闘病生活の後、永眠。1987年の皐月賞、菊花賞を制した二冠馬は、流れ星のように逝った。
サクラスターオーの葬式に出席した平井師は、サクラスターオーのトレードマークだった白いメンコを馬頭観音に収めなかった。
「天国に行ってまで、走らなくていい・・・」
それが、平井師の想いだった。彼の亡骸は故郷の藤原牧場へと帰り、母のサクラスマイルとともに、今も静かに眠っている。
『宿命』
誕生と同時に母を亡くして人間の手で育てられたサクラスターオーは、その栄光を手にする直前に育ての親まで亡くした。さらに、その事実も知らずに臨んだクラシック戦線では、「最も速い馬」「最も強い馬」としての勲章を手にしながら、「最も幸運な馬」には挑戦することさえ許されぬまま、三冠の夢を絶たれた。しかも二冠の栄光を手にしたその直後に、中山の第4コーナーに待っていた破滅の闇へと足を踏み込んだ彼、そのまま奈落へと呑み込まれていったのである。幸せの影の薄い馬だった。
サクラスターオーというサラブレッドは、生命を賭けて戦うサラブレッドの宿命をどの馬よりも激しく、どの馬よりもはかなく体現した馬だった。細い4本の脚で巨体を支えるばかりでなく、最大時速60km/h以上のスピードでターフを駆け抜けなければならない彼らは、競馬に臨む際は、常に死の危険と隣り合わせである。サラブレッドにとっての宿命自体がそうであるのに、彼の場合、それに加えて脚に生まれながらの奇形を抱えていた。ターフとは、サクラスターオーにとってあまりに危険な戦場だった。それでも、サクラスターオーは臆することなく危険な戦いへと身を投じ、極限の走りによって二冠の栄光を勝ち取った。
日本の国花ともいわれる桜は、満開時の美しさと並んで、一斉に散りゆく散り際の儚さを称えられることが多い。その花の名を背負ったサクラスターオーもまた、自らが迎えた3度目の桜の季節に美しく花を咲かせ、その半年後、菊の季節にもう一度狂い咲き、そして4度目の桜が散った後、天へと昇っていった。あまりにも速く、あまりにも強く、そしてあまりにも運に恵まれなかった彼が殉じた美しくも儚い宿命を、私たちは悲しむ。
サクラスターオーの栄光と死から、季節は幾度も巡っていった。現在の競馬ファンの中には、サクラスターオーの名前、あるいは存在自体を知らないファンも増えている。だが、昔も今も、競馬そのものの本質・・・サラブレッドの生命を賭けた戦いという点は、なんら変わりがない。レース中の事故によって多くの馬、そして時には騎手さえ命を落とす。
競馬の宿命・・・その字面だけを言葉で語り、筆で著すことは簡単である。しかし、その実態はあまりにも重く、限りある言葉や筆によってすべてを語り尽くすことなど、できるはずもない。私たちにできることといえば、ただ忘れないこと、あるいは知ることだけなのかもしれない。かつて、彼はそこにいた。多くの悲運を背負った1頭のサラブレッドがいたところには、常に生命を賭けた走りがあった。そして、競馬界に流れ星のように輝いた彼もまた、最後はサラブレッド、そして競馬の宿命に殉じ、散りゆく桜花のように儚い生涯を終えた。それは、歴史の中の事実である。
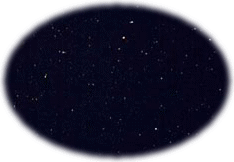
かつて、戦いにすべてを捧げ、生命を賭けたサラブレッドがいた。いくつもの過酷な運命をくぐり抜け、王者としての道を歩み始めたかに見えた彼の上を、流れ星は落ちてゆく・・・