サクラチヨノオー列伝~府中に咲いた誓いの桜~
『祭りの後』
こうして見事第55代ダービー馬の栄冠を勝ち取り、さらに自らを「強いダービー馬」として認知させることにも成功したサクラチヨノオーだったが、彼の競走馬としての戦いは、まだこれからのはずだった。
ダービーの翌週、やはり東京競馬場に陣取ってニュージーランドトロフィー4歳S(Gll。現ニュージーランドトロフィー。年齢は当時の数え年表記)を観戦した境師の視線の先にいたのは、秋以降サクラチヨノオーの強大なライバルとなるであろうオグリキャップだった。スタートからゴールまで、馬なりのままで後続に7馬身差をつけて圧勝したオグリキャップの姿を目の当たりにした境師は、レース後こう語った。
「噂どおり強かったね。いずれ対戦するだろうけど、今から楽しみだよ・・・」
この時の境師には、やがて最優秀4歳牡馬の地位をかけて激突するであろうライバルに対する闘志と勝つための秘策が燃え上がっていたに違いない。
しかし、ダービーでの激走の影響か、サクラチヨノオーはオグリキャップとの対決どころか秋競馬すら待つことなく、右前脚浅屈腱炎を発症してしまった。秋は菊花賞戦線へと向かう予定だったサクラチヨノオーだったが、すべてのローテーションは白紙に戻され、長期休養に入ることになった。
屈腱炎といえば、サクラチヨノオーの父であるマルゼンスキーの競走生命をも奪った業病である。種牡馬マルゼンスキーは、その産駒には走る子ほど脚部不安という欠点まで伝えてしまうという悲しい宿命を背負っていた。サクラチヨノオーだけでなく、初期の代表産駒で菊花賞を勝ったホリスキー、後期の代表産駒でやはり菊花賞馬となったレオダーバンも、やはり最後は屈腱炎でターフを去っている。彼らが能力とともに受け継いだ業病は、父の血がもたらした悲しい宿命だった。
『虚しい期待』
屈腱炎で長期休養を余儀なくされたサクラチヨノオーだったが、その走りたい気持ちまで奪われることはなかった。最初は馬の温泉で療養生活を送ったサクラチヨノオーだったが、やがて症状が落ち着いて放牧場へと出されるようになると、人間の指示もないのに放牧場を走りまわるようになった。その姿は、一刻も早く戦場に復帰したいという彼自身の心の叫びを表しているようだったという。
また、サクラチヨノオーが休養している間の競馬界は、彼の半弟サクラホクトオーの登場によっても盛り上がりを見せた。兄が朝日杯3歳Sを制した時の戦績は4戦3勝だったが、弟は無敗の3連勝でこのレースを制したばかりか、兄が取れなかった最優秀3歳牡馬の地位も獲得した。
「兄をも越える器かもしれない」
そう噂される弟の登場は、兄弟によるダービー連覇、そして夢の兄弟直接対決の夢を膨らませるものであり、そのためにも兄には一刻も早い復帰が期待されていた。
しかし、1年ぶりにターフへと帰ってきたサクラチヨノオーに、かつての輝きが戻ることはなかった。安田記念(Gl)に久々に姿を現したサクラチヨノオーは、もうかつての彼ではなかったのである。
『さらばターフよ』
1年近い休養から復帰したサクラチヨノオーは、当初古馬の中長距離路線の王道として、天皇賞・春(Gl)を目標とするはずだった。しかし、長期休養明けのサクラチヨノオーは、前にも増して行きたがる癖がひどくなっており、中長距離戦線のゆったりとした流れの中では、とても辛抱できそうになかった。これを見た境師は、天皇賞・春(Gl)を諦めて安田記念(Gl)から始動することにした。境師はもともとサクラチヨノオーをマイル向きではなく中長距離向きと考えていただけに、これは苦渋の選択だった。
安田記念当日、サクラチヨノオーは約1年ぶりのレースであるにもかかわらず、3番人気に支持された。確かにこの年の安田記念の出走馬は手薄であり、Gl勝ち馬はこの日出走した17頭中サクラチヨノオーただ1頭だけだった。実戦は1年ぶりで、それも屈腱炎明けの馬がこれほどの人気に支持されたという事実は、ファンがサクラチヨノオーのことを忘れてはいなかったことを証明している。
しかし、サクラチヨノオーはファンの信頼に応えることができなかった。第4コーナーまでは往年の彼を思わせる好位からのレースを進めたものの、直線に入るともう彼の脚は一杯になっていた。小島騎手の懸命の鞭もむなしく、1年前に栄光を手にした東京競馬場の直線で、彼は格下の馬たちにみるみる抜き去られていった。
続く宝塚記念でも、16頭中4番目の支持を受けたサクラチヨノオーは、今度は第3コーナー過ぎでみるみる後退し始め、勝ったイナリワンから遅れること4秒8の最下位に沈んだ。3歳春までとはあまりに違うその惨めな内容に、ファンは目を覆わずにはいられなかった。
そして、この日のレース中に屈腱炎を再発させたサクラチヨノオーは、これを最後に、現役を退くことになった。「サクラ軍団」と小島騎手に2度目のダービーをもたらし、さらに悪化しかけていた両者の関係まで見事に立て直したサクラチヨノオーだったが、彼自身の競走生活は、まるですべてをダービーで燃え尽きてしまったかのように終わってしまったのである。
『滅びざるもの』
通算10戦5勝で引退したサクラチヨノオーは、内国産のダービー馬、そしてマルゼンスキーの後継種牡馬として、その血を馬産地に広げる役割を期待されて種牡馬入りした。
サクラチヨノオーの初年度産駒から出現したサクラスーパーオーは、抽選で出走を果たした皐月賞(Gl)で、人気薄ながら2着に入った。愛知杯(Glll)を勝ったサクラエキスパート、ウインターS(Glll)を勝ったマイターンらの重賞ウィナーも輩出したサクラチヨノオー産駒は、中級クラス以上でもそこそこの活躍を見せた。
しかし、サクラスーパーオーは、父子制覇を賭けた日本ダービーを目前にして、祖父、父と同じ屈腱炎に倒れ、大成することなくターフを去ってしまった。他の産駒たちもGlllクラスでの活躍までであり、Glの夢を見させてくれるほどの大物は、ついに現れなかった。
サクラチヨノオーの半弟サクラホクトオーも、現役時代はクラシック無冠に終わり、セントライト記念(Gll)とAJC杯(Gll)を勝ったにとどまった。そんな弟も、種牡馬として初年度産駒からクラシック戦線に乗ったサクラスピードオーを出したものの、その後の産駒が鳴かず飛ばずとなったことから、兄より先に種牡馬を引退したばかりか、2000年3月16日、腸捻転で早すぎる死を迎えてしまった。幸いにしてサクラチヨノオーの全兄にあたるサクラトウコウの系譜から天皇賞(秋)を勝ったネーハイシーザーが出現したものの、内国産種牡馬受難の時代の中で、そのサイヤーラインをさらに伸ばすことはできなかった。
サクラチヨノオー自身も、1995年から2000年まで6年連続でサイヤーランキング100位以内に顔を出し、97年には最高成績として41位(サラ総合)を残したものの、大物を出さないと人気につながらない種牡馬の世界で、その人気は先細りになっていった。2002年生まれの世代を最後に種牡馬生活に見切りをつけられたサクラチヨノオーは、功労馬として余生を過ごしていたが、2012年1月7日に死亡している。マルゼンスキーの血の継承者として、そして日本競馬の最高峰であるダービーと、近年の種牡馬にとって成功するための必須条件である仕上がりの早さを証明する朝日杯の両方を制したサクラチヨノオーではあったが、種牡馬として期待通りの成績を残したとは言えないことは、非常に残念であると言わなければならない。
このように、競走馬としては、多くの人々の誓いを背負う形で見事「昭和最後のダービー馬」となったサクラチヨノオーだが、「昭和」はとうの昔に終わって「平成」から「令和」に移り、またサクラチヨノオーに関わった人々も、全氏は鬼籍に入り、境師はもちろんのこと、小島騎手も騎手を引退して調教師に転身し、そして調教師も引退している。
だが、サクラチヨノオーと直接関わっていた人々が競馬界から去っていったとしても、彼らがサクラチヨノオーとともに成し遂げた物語までが輝きを失うわけではない。「彼自身のドラマ」である種牡馬としての血統を後世につなぐことはできなかったサクラチヨノオーだが、彼の物語が忘れられない限り、その存在が滅びることはない。
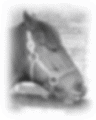
馬主、調教師、騎手、自らの血・・・それらに宿命づけられるダービーへの誓いとともに始まった彼の戦いは、昭和最後のダービーの終結によって完全燃焼したのである。